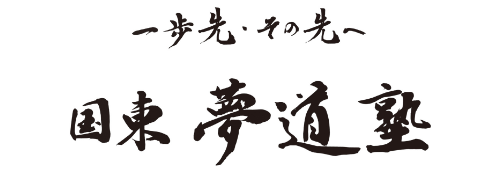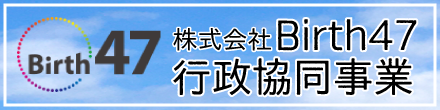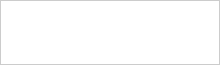国東高校も新学期がスタートしましたね。
7月から夢道塾にやってきました、秋吉です。
国語やその他、一緒に頑張りましょう。
よろしくお願いします!

まだまだ暑い日が続きそうです💧
熱中症対策はまだまだ必須ですね。
8/23からは二十四節気の『処暑』で、9/7からの『白露』の前日、9/6までがその期間にあたります。
いわく、「暦の上で暑さがおさまるころ、昼間はまだ残暑の厳しい日もあるが、朝夕の風は少し涼しくなる」と…
いや、暑いんだが?
そもそも、8/8が『立秋』「暦の上では、秋です」とか、夏真っ盛りだが?
と、思いますよね?
正解です。
この『暦の上』ではという決まり文句、習った人もいるかもしれませんが、
これは明治時代より前に使用されていた暦のことで、「旧暦」と呼ばれています。
今の暦と一か月くらいの差があります。
なので、明治時代より前の古文では季語なども多少ズレているので注意です。
詳しく説明すると、
明治維新後の日本は海外との交流が活発になり、色々なものを世界の基準に合わせていきました。
例えば、時刻の表し方もそうですが、一番はこの暦です。
地球が太陽を1周するのを1年とする、太陽暦ですね。
当時の日本や東アジアの国は
・太陰暦で月の満ち欠けで日数を計算(新月から次の新月まで30日)
・太陽暦で季節を区切る(日の出と日の入りの位置がちょうど東西の時など)
この、太陰暦と太陽暦を合わせた「太陰太陽暦」を使用していました。
さて、暦を海外に合わせた明治5年12月2日…
翌日は何年何月何日になったと思いますか?
もちろん、12月3日ではありません。
なんと
明治6年1月1日
当時は年末年始の準備に余裕がなく大変だったとか…
さて、もう1つの問題は、1ヶ月のズレと年中行事です。
・新暦の同月同日に行うもの(七夕など)
・新暦で1ヶ月後の同日に行うもの
・太陽の動き、月の満ち欠けに関連するので新暦になっても関係ないもの(中秋の名月など)
と、それぞれで、これまた当時の人々は混乱したのではないでしょうか…
こんな、ちょっと勉強になったり、そうでもなかったりしたことを書いていきたいと思います。
良かったら、暇つぶしにでも読んでくださいね!