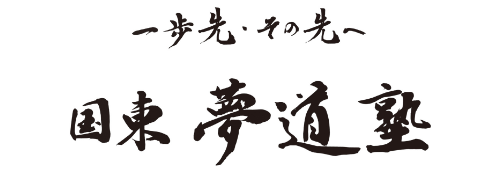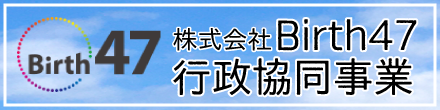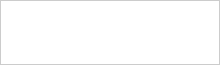こんにちは!
国東夢道塾、秋吉です。
さて、今が旬のみょうが。
皆さんは好きですか?

そうめんの薬味や、てんぷら、甘酢漬けなど
漢字では「茗荷」と書きます。
食用に積極的に栽培、食しているのは日本だけで、
歴史は古く、魏志倭人伝に記載があったり、
奈良時代にはすでに栽培が始まっていた、などなど
中国では漢方薬として使われるそうです。
近年ではその風味に着目した各国のシェフ達がデザートやカクテルとして使用することもあるらしく、
(なにそれ、おいしいの?!🙄)
呼び名は「Japanese ginger」、「Myoga」、「Japanese Myoga」など
食欲増進、消化促進、発汗作用、血行促進、抗菌作用があるといわれています。
私、秋吉は、幼いころ、
とある昔話を読んでからというもの
「みょうがはヤベェ😱」
という先入観が抜けず、
あの独特の風味も苦手です…
さて、その昔話、
岩手県の話で、ジャンルは笑い話です。
とある宿屋の夫婦はとても欲張りで、
お客の忘れ物などを自分のものにしていた。
ある日、高価そうな荷物を持ったお客がやってきたので、
なんとか荷物を忘れるように、と、
食べると物忘れをするというみょうがをたくさん食べさせた。
お客はみょうがが大好物で、たくさん振舞われたみょうがをたいらげ、
翌日、宿代を払うのを忘れてご機嫌で去っていった。
と、いうお話。
さて、この
「みょうがをたくさん食べると、物忘れをする」
というのはもちろん、迷信です。
この迷信のもととなった逸話を調べてみると、
インドの仏教に辿り着きました。
お釈迦さまの弟子、周利槃特(しゅりはんどく)は、
生まれつき物覚えが悪く、自分の名前も覚えられなかったため、
自分の名前を書いた板を首から下げて名前を聞かれたときにその板を見せて名乗るほどでした。
ある時、あまりにも愚かなので兄にも諦めて家へ帰るように言われ、悲しんでいると
お釈迦様は
「悲しむ必要はない。おまえは自分の愚かさを知っている。
世の中には賢いと思っている愚か者が多い。
愚かさを知ることは、最もさとりに近いのだ」
これを聞いて、20年努力し、ついに周利槃特(しゅりはんどく)は悟りを開きました。
死後、彼の墓の周りに見慣れない草が生えてきました。
その草を何と呼ぶか考えたとき、自分の名前が覚えられず、
名前を書いた板を背負っていたことから「名」を「荷(にな)う」
ということでその草に「茗荷」と名前を付けました。
…つまり、これは「無知の知」!💡
仏教にもギリシャのソクラテスの「無知の知」の考えがあるのは初めて知りました!
神話などに、何故か世界に共通する部分があるのは知っていたけど、
思想にも共通点があることがあるんですね。
なるほど、
異なる手段や方法があっても、最終的には同じ目的地や結論にたどり着く
という意味の古代の格言、
「すべての道はローマに通ず」
とは、こういうことですね。