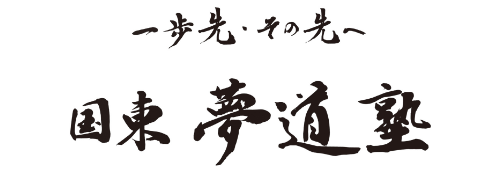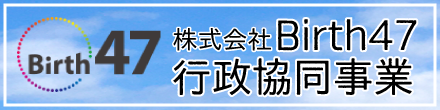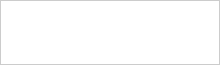本日、国東高校「秋の園芸フェア」だそうです!
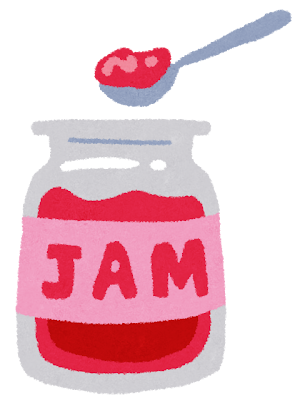
そんな本日は「立冬」ですね。
「冬の始まり」を意味します。
木枯らしが吹いたり、
朝晩の冷え込みが厳しくなったり、
本格的な冬の到来を告げる時期です。
冬物の衣類や暖房器具の準備を始める目安とされています。

が、細長い日本。
ブログやXでは
北海道の教室は
もう既に準備完了しているところもある様子です。
…大分県?
まだ20℃予報の日もあるんだぜ…?
しかし、日が落ちると冷えるため、
暑がりな私、秋吉も
ついに本格的に上着着用。
…今までどこにあるかわからなかったのを
やっと発掘できましたよ。
細長いといえば、
東京あたりから九州方面に
飛行機で夕方フライトすると、
ずっと夕日を追いかけて不思議だそうです。
東の親戚と電話なんかすると、
あっちはもう日が沈んでるけど、
こっちはまだ夕方、なんてこともあります。
さて、「今日から冬です!」って暦に言われましたが…
今回は、暦の話はしません。たぶん。
季節が移り変わる節目、
つまり、
「季節」を「分ける」
「節分(せつぶん)」
です。
でも一般に「節分」といえば、
2月3日のことですよね?
「立春」の2月4日の前日に
「豆」=「魔滅」をまいて
鬼、つまり病や災いを追い払う行事です。
コンビニの全国展開により、恵方巻もすっかり定着しましたね。
もともとは江戸時代くらいから
関西で商売繁盛を願って始まったとされるものです(諸説あり)、
「まるかぶり寿司」とも言います。
まだ、国東にコンビニなど皆無の時代、
京都の大学に行ったときに時に初めて知りました。
他には、諸説も名前もいっぱいの、
回転焼き、大判焼き、小判焼き、今川焼き…
あれも、関西では頑なに
「御座候(ござそうろう)」
と呼びます。
某ハンバーガーチェーン店も
「マック」ではなく、頑なに「マクド」と呼びます。
あと、大学の入学から何年目か
これも地域によって「〇年生」か「〇回生」で違います。
関西では「〇回生」でした。
さて、話を戻して、
ここで浮かぶ疑問。
季節って4つですよね?
立夏、立秋、立冬の前日は?
「節分」じゃないの?
もともとは4回あったようですが、
旧暦では立春が1年の始まりにあたり、
1年の始まり、春の始まりと尊ばれ、
「節分」といえば春のみになっていったようです。
また、古文常識必須、年末大晦日の行事の「追儺(ついな)」
旧暦ではここが立春前日の大晦日となりますね。
つまり2月3日です。
旧年の厄や災難を祓い清める儀式ですね。
別名「鬼遣(おにやらひ/おにやらい)」👹
こっちのほうがイメージが一致して覚えやすいかもしれません。
寺院では「節分会(せつぶんえ)」の法要、
神社では「節分祭(せつぶんさい)」の神事が行われるようです。
それにしても、消えた3つの「節分」…
何かしらの行事があったはずでは?
と、思いますよね。
江戸時代までは年4回あったとか。
…詳しくは調べ学習の題材にしてもいいですよ!
神社仏閣の宝庫、国東半島ならではの学習ができるかも?