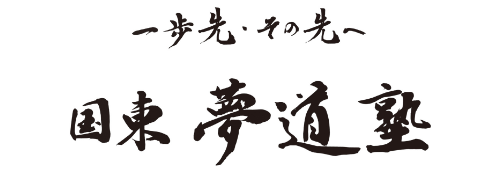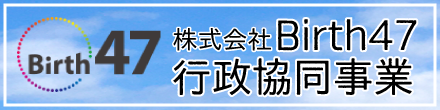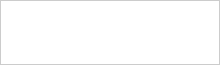こんにちは!
国東夢道塾、秋吉です。
ようやく雨が降ったり、曇ったりした日に暑さも和らいでいるような?
そんな気がしなくもない昨今。
さて、昔から
「暑さ寒さも彼岸(ひがん)まで」
といいますが、どういうことでしょうか。
まず、「彼岸(ひがん)」を知るには
太陽がちょうど東(真東)から出て、ちょうど西(真西)へ沈む日
昼と夜の長さがほぼ同じ日、
「秋分の日」
を、知るべし!
暦でいうと(過去ブログ参照)天体観測により定められた祝日です。
厳密にいうと、多少昼のほうが長く、
ちょうど同じ日は「秋分日」として区別されるそうです。
1年のうち、昼間の時間が最も長い日が「夏至」。
それからだんだん短くなって、昼と夜がちょうど半分ずつになるのがこの日です。
今年は23日ですね。
お休みですよ!😄
そしてこれ以後は、昼の時間のほうが短くなり、
1番、昼が短く、夜が長い日が「冬至」となります。
天体的にちょうど夏と冬の半分ということです。
では、ここから「彼岸(ひがん)」の説明です。
仏教では、生死の海を渡って到達する悟りの世界のことを「彼岸(ひがん)」
この世の世界のことを「此岸(しがん)」
といい、悟りの世界は西方浄土といい、西の彼方にあると考えられてきました。
つまり、太陽が真西に沈むことから、「彼岸」に通じやすくなる日として
「お彼岸(おひがん)」
と呼んで、お墓参りなどをして、先祖供養を行うようにしたのです。
その期間は秋分の日を中心にした前3日と後3日の7日間になります。

さて、ここで敏い人は
「なんか似たような日があった気がする」
と、気づくはずです。
そう、「暑さ」は秋分の日まで
では、「寒さ」は?
冬至を過ぎると、また昼の時間は徐々に長くなっていきます。
そして1番長い夏至になるまで
もう1回、昼と夜の長さが同じ日がありますよね?
そう
「春分の日」
もちろん、こちらも「お彼岸(おひがん)」として7日間に先祖供養を行います。
辛い暑さや寒さもいずれは自然と、必ず和らいでいくものです。
それも表しているので
『辛いことも、いずれ時期が来れば去っていく』
という意味のことわざとしても使われます。
さて、次回は、
この「お彼岸(おひがん)」のお供え物のアレのお話をしますね。
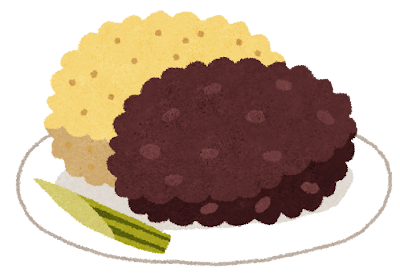
お楽しみに!